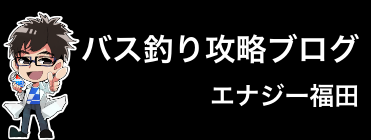どうも、エナジー福田です。今回は「デカバスを釣るために意識している6つのポイント」についてお話しします。
よく「どうやったらデカバスが釣れるのか?」と聞かれますが、実際には特別な裏技はなく、誰でも真似できるシンプルな考え方と行動の積み重ねです。僕自身も5年前は普通にバス釣りをしていて、今思うと効率が悪いこともたくさんしていました。しかし試行錯誤を重ねていくうちに、デカバスが釣れる確率が少しずつ上がってきたんです。
今回は、その変化を整理した6つのポイントを紹介します。これを意識することで、大きなバスに出会えるチャンスがぐっと増えるはずです。
この記事の内容は動画でも解説しています。時間がある方はこちらからどうぞ!
1. ルアーサイズを大きくする
デカバスは「一撃でお腹を満たせる餌」を好みます。小さなベイトを追い回すより、大きなベイトを一発で捕食したほうが効率的だからです。
僕がよく使うのは、スライドスイマー175やブルーシューターJr. といった大きめのルアーです。手のひらサイズのワーム(4インチ〜5インチ前後)もよく使います。これらはビッグベイトほど派手ではありませんが、小さすぎず、大きすぎない絶妙なサイズ感でデカバスを狙いやすいです。
逆にベビーポッパーや小型ミノーのような小さなルアーは、小バスが多い状況では効果的ですが、デカバス狙いの効率は落ちます。実際に僕も春の一時期、サイコロラバーやホバストのような小さなルアーで大きなバスを釣ったことがありますが、それは「その場にデカバスしかいない」と確信できる状況でした。
普段から闇雲に小さいルアーを投げていると、どうしても小バスの数釣りになってしまいます。デカバスを狙うなら、まずは大きめルアーを主体に考えることが大切です。
2. バスが何を狙っているのかを見極める(マッチ・ザ・ベイト)
「マッチ・ザ・ベイト」という言葉はよく聞きますが、これは本当に重要です。バスが実際に捕食しているベイトの種類・サイズ・色にルアーを近づけることで、反応が格段に変わります。
僕が特に実感したのは、琵琶湖でモロコを捕食しているバスを狙った時です。小魚のサイズを観察し、それに近いメロG 5.2インチを使ったところ、反応が一気に良くなりました。さらに動きの面でも、一般的なワイヤーのアラバマリグよりも「ふわふわした動き」が出る特定のリグの方が、より自然にモロコに近づき、デカバスの反応が明らかに良かったのです。
表層なのか、ボトム付近なのか。どのレンジでベイトを食っているかを観察することも大切です。例えば、表層に小魚がざわついているなら表層系のルアーを、ボトムでベイトが溜まっているならボトム系のルアーを選ぶ。このように「今バスがどこで、何を食べているのか」を見極めることで、釣果は大きく変わります。
3. 粘らずランガンする
デカバスを狙うとき、僕は「粘らない」ことを徹底しています。
琵琶湖は広大ですが、南湖だけでも一日で回れる範囲は限られています。その中で、気配がなければ数投だけしてすぐに見切り、どんどん次のポイントへ移動します。実際、僕は1日釣行すると「足がパンパンになる」くらい歩き回っています。
下見の段階では、竿を持たずにアイスコーヒー片手に岸際をチェックすることも多いです。釣れる気配がある場所を見つけてから竿を出すほうが効率的だからです。
ルアーサイズが大きいと、勝負が早いのもメリット。数投して反応がなければ、次のポイントへ移動する。このテンポの良さがデカバスとの遭遇確率を高めてくれます。
4. タイミングを変えて入り直す
同じ場所でも、時間帯や条件次第で状況は一変します。
例えば、昼に訪れたときは無反応だったポイントでも、夕方に風が吹いて水がざわつくと急にバスが口を使うことがあります。ベイトフィッシュの接岸タイミングも大きな要因です。
僕は一級ポイントでは「ダメでも数時間後に入り直す」ことをよくやります。実際に、午前中は不発だったのに、午後になって風が変わったタイミングで50アップが釣れたこともあります。
短時間で色々なルアーを投げすぎると警戒されるので、時間的に余裕があれば「タイミングを変えて再挑戦」する方が効果的です。
5. 釣れないときは仕方がないと割り切る
デカバスはもともと数が少ない魚です。
30cm前後の小バスは多くても、40アップ以上、特に50アップ以上となると、個体数は一気に減ります。そのため「釣れない時間があるのは当たり前」と割り切ることも必要です。
僕自身も以前は「釣れない=焦る」という気持ちが強く、無理に小バス狙いに切り替えてしまうこともありました。しかしそれではデカバスに近づけません。釣れない日があっても、それは自然なこと。数少ないチャンスを信じて続けることが大切です。
6. 釣れた後に理由を考える
最後に最も大事なのは「なぜ釣れたのかを考えること」です。
例えば、アラバマリグで釣れたなら「その時ベイトが群れていたからだ」とか、「風が吹いて水が濁ったから口を使った」など、理由を突き詰めることが次の釣行に生きます。
コバスは気まぐれで食ってくることがありますが、45cm以上のデカバスは必ず理由があってルアーに口を使っています。その理由をパターンとして積み重ねていくことで、再現性のある釣りができるようになります。
僕自身も冬の釣行で、ネコリグをひたすら投げ続けたことがあります。同じルアーを投げ続けることで、「どのタイミングで口を使うのか」を把握できるようになりました。流れが変わった瞬間やベイトが寄ったタイミングなど、釣れる理由を理解すると釣りが一段と面白くなります。
まとめ
デカバスを狙うために僕が意識しているポイントは以下の6つです。
- ルアーサイズを大きくする
- マッチ・ザ・ベイトを意識する
- 粘らずランガンする
- タイミングを変えて入り直す
- 釣れないときは割り切る
- 釣れた理由を考えて次につなげる
これらを一気にすべて実践する必要はありません。僕も少しずつ取り入れて身につけてきました。まずは「ランガンする」「ルアーサイズを大きくしてみる」といった部分からでもOKです。
少しずつ試していけば、確実にデカバスとの距離は縮まります。ぜひ実践してみてください!